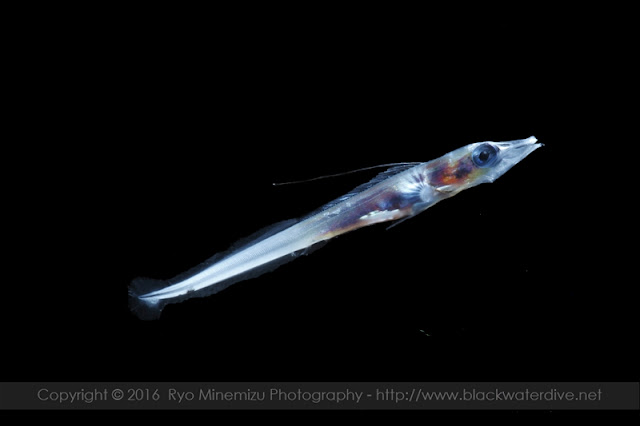This individual was found in -5m at Osezaki Shizuoka Japan on 27th November 2014.
Osezaki is a part to coast of Suruga Bay.
This individual size is about 100mm ML.
 |
| Dorsal view of Amphitretus pelagicus |
 |
| Lateral view of Amphitretus pelagicus |
Eyes like a periscope, it's to the dorsal side.
 |
| Arms and web of Amphitretus pelagicus |
Suckers is one row at proximally and two rows at near the tips.
 |
| Upside-down pose of Amphitretus pelagicus |
Arms can enclose the head. Perhaps, it's for defense.
REFERENCES:
Amphitretus - Tree of Life Web Project
Jereb,P., Roper,C.F.E.,Norman,M.D.,Julian,K.F., 2014. Cephalopods of the World. An annotated and illustrated catalogue of Cephalopod species known to date Volume 3 Octopods and Vampire Squids. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No.4, Vol.3. 382pp.